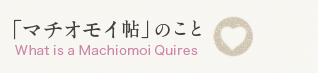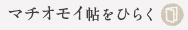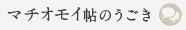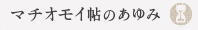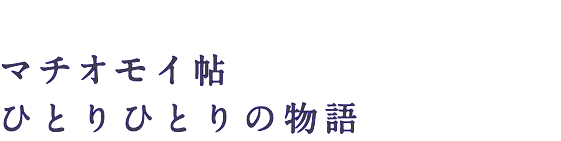
「マチオモイ帖」は、町のガイドブックではありません。ふるさとの風景や幼き日の思い出を綴ったアルバムのような冊子もあれば、失われた町や、町に封印していた苦い記憶をこじ開けたような私小説風のもの、なつかしくもなんとない町と自分との距離感を淡々と撮影した写真集、おばあちゃんの生きる知恵をイラストにしたやさしい絵本など、内容はさまざまです。ここでは、ひとりひとりの物語のほんの一部をご紹介します。


「生まれそうになったら/みかんの丘にむかって/黄色い旗をふる/それが私の生前に交わされた26才の父と22才の母の世紀の約束/黄色い旗が見えたら/すぐに山から降りるけぇ/それは、ケータイなんてないころの/やさしい約束」――これは、マチオモイ帖の原点となった『しげい帖』(広島県尾道市因島重井町)の冒頭に綴られた一遍。穏やかな瀬戸の島に生まれた村上美香さん(コピーライター)が幼い頃に伝え聞いたエピソードを詩にしたもの。畑仕事を休めないお父さんは、みかん畑から日に何度も海沿いにある家の方を振り向いていたという。昭和40年代、瀬戸の島では産婆さんによるお家での出産が主流。引き潮も、満ち潮も、フナムシも、トビウオもみんな生まれてくる新しい命を待ちわびた。「忘れそうになったら、海に帰ってきんさいね。ひとりで生まれたわけじゃない。ひとりで生きてくきみじゃない」。

26才のグラフィックデザイナー森田梨加さんは3才になる愛息子「ゼンくん」と犬のミシェルとの3人暮らし。ひとりで育てると決めた日から、自宅をシゴト場に近い都心に引っ越した。出来るだけいっしょにいる時間が持てるように「ママは、きみのフルサトをこのマチに決めた」。森田さんの『ホリエ帖』(大阪市西区堀江)はそんなママから小さな君へのオモイをぎゅっと詰めたタイムカプセル。子どもでも繰り返してページをめくれるようにカラフルな布絵本として仕上げた。マジックテープをびりびりと剥いでページを開くと堀江のミルクショップや、浪速筋の銀杏並木、日曜日に公園で食べるハンバーガーのポップなイラスト。「今、見えているもの、今、ふれているものを、大人になっても忘れないで」「なるべくたくさん楽しいことをこのマチでつくっていこう きみのステキなフルサトになるように」。それは、小さなママの大きな決意。


小学3年生から一眼レフを持ち歩いていたカメラマンの余 有奈さん。カメラを持っていない日には「のうみそがフィルム役で、目がシャッター役だけぇね」と弟に教え、きれいなものに出会うたびに「なんべんもなんべんも“まばたきシャッター”を押した」。余さんの『とうはく帖』(鳥取県東伯郡東伯町)づくりは、撮りためていたフィルムを十数年ぶりにプリントすることからはじまる。夏休みの弟、七匹も生まれた仔犬、最新カットのヘアサロン、ラムネ瓶に刺したガーベラ、ごはんの匂い、お姉ちゃんがB’sを大音量で聞いている音まで蘇えってくる。家族の反対を押し切り、カメラマンになって6年。娘が恋しいお父さんは帰省するたびに「家を改造して、暗室を作ってやろうか?」と持ちかけてくるという。とはいえ、余さんにはまだカメラマンとして深めてみたい世界がある。『とうはく帖』に収めた写真に夢中な少女時代のジブンには負けていられない。



リンゴが美味いベ!とはじまる『やいた帖』(栃木県矢板市)。そこは、現在大阪で仕事をしているグラフィックデザイナー成瀬孝一さんのふるさと。数年前、お父さんが病気になってからは休みのたびに戻るようにしていたがオモイは距離を越えることができなかった。オモイやムネンを手繰り寄せるように成瀬さんは、久しぶりに今はお母さんが静かに暮らす矢板の町をめぐった。お母さんは、お好み焼きやランチ、仕出しまでを請け負う「アミューズ」という喫茶店を切り盛りする明るい女性。町の憩いの場でもあり、成瀬さんもこの店で育ったようなもの。「営業中」と書かれたお店の姿こっそり写真に収めて、マチオモイ帖に載せた。しかし、『やいた帖』が出来上がった数ヵ月後、お母さんは数十年間も大切にしてきた店を閉めることに。「ここは、あたたかいっぺ。あなたは、あたたかいっぺ」――『やいた帖』は無口な息子から、お母さんへの感謝状となった。

「むかし鶴がぎょうさんおったから、鶴町になったんやて!」――『Crane Town~鶴町帖』(大阪市大正区鶴町)と名付けられたヴィジュアルクリエイター・仲里“プーリー”カズヒロさんのマチオモイ帖は、小学生の頃に聞かされた町伝説の真相を確かめるところから始まった。仲里さんはマチオモイ帖の取材のために久しぶりに「鶴町」を訪ねてみた。防波堤や、渡船場、小学校、そのすぐ近くにある昔よく通っていた文房具屋さんに立ち寄ってみると、今もお店を開けているご夫婦に再会。当時の話から鶴町の歴史まで話が尽きなかった。仲里さんは店のご主人に聞いた話からアイデアを広げて『鶴町帖』を完成させる。1冊をご夫婦にプレゼントすると、後日、丁寧な字で綴られた手紙が届いた。ご夫婦は、小学校時代に本が大好きだった仲里さん兄弟を今も鮮明に覚えているという。覚えてくれている人がいる。なにもないと思っていた町が宝箱に変わった。